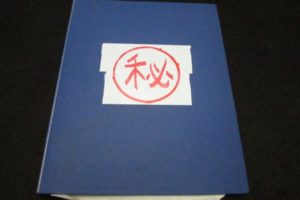農地を農地法第5条の転用申請許可を受けて購入する事になりましたので、その申請過程や手続きについて書いてみます。
もちろん、購入する人の要件や、売却する農地の立地条件によって、そもそも転用許可が認められない場合も存在しますので、一例として捉えて頂ければと思います。
購入した農地
大まかな流れはこんな感じです。
Contents
農地法5条申請による転用許可申請
農地法5条申請の申請書は簡単です。
各自治体のホームページ等よりダウンロードできると思いますが、名前や面積などの必要事項を記入するだけでo.kです。
記載例についてはこちらが詳しく書かれていましたので参考にして見て下さい。
手間がかかるのが必要書類の作成です。
必要書類について
- 1~4については簡単ですね。関係者が署名押印し、全部事項証明書等の書類を法務局で入手したりすれば完了です。
- 5番については、申請地の周辺不動産についての調査をし、公図にそれぞれ記載が必要ですが、これもそこまで難しい事ではありません。
全部事項を入手・確認し、現況と照らし合わせ記載すれば良いだけです。 - 6番については測量図が法務局にあれば簡単です。
多くの場合、売却と同時に測量士さんへ依頼し測量を行うので、図面の入手は簡単です。
測量を行わない場合は現況の図面を作成する必要がありますが、地域によっては境界査定が必要な場合が多いので、基本的には測量する必要があると考えていた方が良いでしょう。 - 7~9については、転用をする事の目的・計画を図面にして提出します。
車の台数や寸法、必要な敷地の面積、建物の計画図、資材などの配置図など、その敷地が必要な根拠が大切になってきます。 - 10については、現在の状況写真によって、違反転用が行われていないか等を確認する事も含め、現況確認の為に写真を四方や道路状況も含め撮影します。
- 11~16については、法人等が事業として転用する場合に必要で、事業目的や内容、資金的な裏付けを求められます。
定款に記載されていない事業の為に転用申請すると言うのはおかしいですよね?
転用申請についての合理性を含めて、確認が必要となります。 - 17・18が1丁目1番地であり、一番大変な部分と言えます。農地転用の申請の大部分は、この作業と言えます。
農道や水路を管理する団体が、転用をする事によって生ずる周辺への影響などを考慮し、意見書・同意書を発行してくれます。
・水路に架橋が必要な場合は、水路についての工事図面が必要ですし、どういった内容の工事を行うのか?について細かくcheckしてくれます。
・敷地の排水計画や造成計画についても、工事図面を提出し、確認してもらう必要があります。
なぜそのような同意や意見が必要であるか?
という疑問が沸いた方もおられると思いますが、こちらが転用行為を行う事で、周辺の農地に影響を及ぼすことが起こり得るからです。
そもそも農地法は農地を守るための法律ですから、周辺に悪影響を及ぼす可能性のある転用行為は認められるとおかしいですから、基本的には問題が起こらないような工事や対処をする必要があると考えておくと良いでしょう。
現段階は、許可申請の提出前の、意見書を作成してもらう段階です。
細かい部分も含めて、追記していく様にしますね^^
近隣からの苦情が入る・・・
農地転用には水路や農道の管理者の意見書や同意書が必要となります。造成工事をする事によって、周辺の農地にどれくらいの影響があるのか?
という事が一つのポイントとなります。
通常、一戸建ての住宅を建設する程度の造成工事と建築においては、周辺に被害を及ぼすことはほとんどあり得ません。
また、今回の現場においても、排水経路確保の為、水路工事(民地内)を別途行い、迷惑を掛けないような体制を取っておりました。
この水路工事については、既に出来上がっている物で、それについて後日取得するという形だったのですが‥‥
近隣の耕作者の方・・・唯一といっていいくらいの耕作者の方から、

うちの畑に雨水が入ってくるから、工事をやり直してくれ!
と言う旨の苦情を、土地改良区に向けて申し立ててくれたのです。
民地の中の水路の事ですし、土地改良区としては権限が無い部分ですが、苦情があった為、それなりの対応をして欲しいとの要請がありました。
こちらとしては、その工事内容についての権限も無い状況なので、一応水量計算をしてもらい(設計士に依頼し)、問題が無い根拠を提示する事としましたが・・・
どうもその敷地の所有者との間で感情的なトラブルを抱えているようで、直ぐには納得してくれそうもありません。
第2の案、第3の案と用意していますが、恐らく当面は納得してくれそうも無いので、排水先を別に確保するようにしました。
わかりにくい話になってしまったかと思いますが、要は、
という形へと変更したという事です。
本来は、突っぱねてもイイお話ですが、時間もかかりますし、丸く収まるのが一番なので、そのような形としました。
農地転用の申請は簡単だと思う方もおられると思いますが、第3者が絡んでくるとすんなりと行かない事も起こり得ます。
理屈的に無茶苦茶を言う方も存在しますし、近隣との関係性は注意が必要な点と言えますね。
土地改良区からの意見書を貰う
まずはやっとのこと上記の経緯を経て、土地改良区からの「意見書」を貰う事ができました。「意見書」を貰う為には、土地改良区の同意が必要です。
その為に今回のケースで必要であった物は、
- 造成工事図
- 架橋工事図
- 分譲計画図(測量図)
- 排水計画図
- 雨水放流についての同意
といった書類です。
今回は宅地分譲なので、分譲計画図でしたが、建物を建築する際は建築図面等も必要になります。
これらの書類を精査した上で、土地改良区が管理している国有地(農道や水路)への影響や、近隣の農地への影響について問題が無い事、そして同意をする事を記した書類が「意見書」なのです。
※地域によってこれらの内容(架橋や雨水放流)について必要な費用の単価が違いますので、その都度調査が必要です。
その後の許可申請作業
さて、ここまでの作業が出来れば後は農地法の要件に沿っていれば簡単です。後は残りの必要な書類を集めたり作成するだけです。
冒頭記載の1~16の書類を集めてくれば、後は正副2部の申請書を作れば問題ありません。
もちろん、事前に農業委員会との打ち合わせもしたうえでですが、記載方法の間違いや誤字脱字等に問題なければすんなりと申請を受け付けてくれるはずです。
5月15日〆の翌月末に許可が下りてくるのを待つばかりとなります。
もし何らかの問題があるようであれば、この期間の間に是正措置の指示があり、その対応をする必要がありますが、ほとんどの場合は致命的な物ではないので簡単な訂正・是正でなんとかなります。
6月下旬、無事に農地転用の許可が下りました。
さてここからの流れですが、所有権を私に移転をし、造成工事に取り掛かる形となります。
冒頭の田んぼの状態から、現在、土地の改良を行い、擁壁を立ち上げる為のベースを打ったところです。
梅雨や台風の影響で工事日程が押し気味ですが、農地転用の申請通りに着々と宅地に仕上がっていっています。
ようやく現場の工事が完了しました。
この後、分筆・地目変更という形で最終作業となります。
当初の売買契約から約5か月で、建築が出来る状態まで仕上がりました。

時間はかかりますが、農地を購入して家を建てる事を考えている場合は、こんな感じの流れになりますので、参考にして下さいね。
やっと宅地への転用が完了した、今日この頃ですが、今更のタイミングでお問い合わせを頂いたりしてます。
この段階ではすでに売却先が決定している事の方が多いです・・・。
なので、農地を自宅などを建てる為に、宅地の状況もしくは見込み宅地として購入しようとされる方は、常にアンテナを張っておく必要があります。
造成工事が始まった時には時すでに遅し・・・とならない為には、事前に情報を入手できる体制を取っておく事が必要なので、信頼できる不動産業者へ打診しておくと良いでしょう。
農地から宅地へ転用後のお話
3日程前になりますが、完成した宅地の近隣の方から、役所へ苦情の連絡があったそうです。
その後、私に連絡があったのですが・・・。
その内容というのは、
地上げをされた事によって自分の敷地内の防犯体制が低くなった
という内容でした。
「地上げをする事で、隣接地からの侵入がしやすくなる・・・どうしてくれるんだ!」・・・という事なのですが・・・。
厳密に言うと、敷地と敷地の間にある50cm程の、ほぼ使われていない農道の高さを上げた事についての指摘なのですが・・・。
こちらとしては農道の管理者及び市と協議をし、
という公共性の観点から、「現状程度まで地上げを一緒に行い対応して欲しい」という要望に応えた結果でした。
わざわざしなくても良い工事を、それなりの費用を掛けて行っているので、突然のクレームには????という疑問の状態でした。

そんな事言われても、地盤面が上がってくる前提で周囲の壁や目隠し等の防犯対策をした訳ではないから、何とか対策してくれないと困る!
時節柄、どこぞの国のクレームと同じ匂いを感じてしまいましたが、個人の利益の主張をされる方と、公共性を重視した事に対応したこちら側との意見の対立の形です。
確かにこれまでと周辺の環境が変わって不安を覚えるのも分かるのですが、それまでの経緯と公共性の事についてやんわりと説明をした次第です。
すると、自分一人では分が悪いと感じたのでしょう。

うち1件だけでは言いたい事を言えないから、被害を被っている北側2件の方含めて説明に改めてきてください!
と言われてしまいました。
隣接の方々も、2年ほど前に大手のハウスメーカーによってなされた分譲地の方々なので、通常は第3者条項の説明があったはずです。
近隣の変化によって環境が変わる事があるという説明ですね。
それを踏まえて土地を購入されているのです。
そのうえで、「自己の防犯が悪くなったから何とかしてくれ」、というのは個人の我がままをこちらへ押し付けてくる行為です。
何とかして欲しいと言われても、こちらもどうしようもありません。
良かれと思ってやった事ですが、こういうクレームも起こるんですね。
結果的には、他の2件の方は安全性の面で自分の子供が落ちこんだりしなくなる為、逆に感謝をされました。
お役所の担当課、管理者にも、「こちらの要望でやってもらった事だから構わない」と返答してもらいました。
現在はこの方だけが我がままをこちらへ言っているだけの状況になっています。
それでもこちらへ意見を押し付けようとするこの方に、どの様にしたら納得してもらえるのか?という答えを出してもらわなければ、この先の対応も返答も出来ない状況ですが、基本的にこちらに落ち度がある事では無いので、対応しようが無いのも現実です。
さて、この某国のような方に納得して頂ける時が来るのでしょうか?
また改めて情況結果については書きたいと思いますが、農地を宅地にする場合には近隣の状況も考慮する必要があるという事ですね。
世の中には多数の常識よりも、個人の常識を押し通そうとする人も居るので、注意が必要であると改めて勉強になりました。